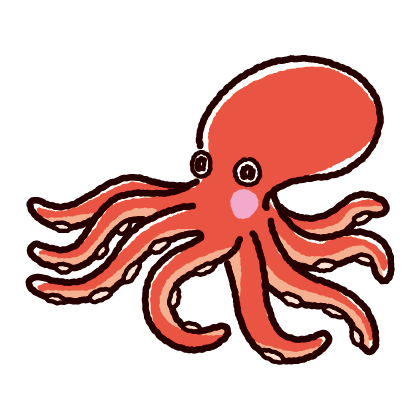海の中でひときわ不思議な存在感を放つタコ。たこ焼きや寿司ネタとしては身近ですが、その生態を知れば知るほど「えっ、そんな生き物だったの!?」と驚く特徴が次々と出てきます。ここでは、科学的な視点からタコの魅力を掘り下げてみましょう。
タコには3つの心臓があり血は青い
タコの体には、実は3つの心臓があります。2つはエラに血液を送る「鰓心臓」、もう1つは全身に血液を巡らせる「体心臓」。興味深いのは、タコが泳ぐときに体心臓が一時的に止まってしまうことです。そのため、泳ぎ続けるとすぐ疲れてしまい、普段は海底を歩くように移動しています。
さらに血液の色も独特です。人間の血が赤いのは鉄を含む「ヘモグロビン」のおかげですが、タコは銅を含む「ヘモシアニン」で酸素を運搬します。このため血は青く、低温や低酸素の環境でも効率よく呼吸できるようになっています。冷たい深海でもタコが元気に生きられるのは、この仕組みがあるからです。
タコは9つの脳を持つ“分散型”の頭脳
タコの知能は動物界でも特に高く評価されています。その秘密のひとつが、脳の仕組みにあります。タコには頭部に「中枢脳」があり、さらに8本の足それぞれに独立した神経節が存在します。合計すると9つの“脳”を持っているとも言えるのです。
実際に、タコの足を切り離しても、しばらくは獲物を捕まえようとする反射行動を見せます。これは足自体がある程度の判断を下せるためで、神経が体中に分散している証拠です。まるで分散処理をするコンピュータのように、タコの体は部分ごとに考えながら動いているのです。
タコは骨のない体と驚異の柔軟性
タコには骨がありません。そのため、体は柔らかい筋肉と皮膚だけで構成されており、信じられないほど狭い隙間を通り抜けられます。直径2〜3センチほどの穴でも、頭の部分さえ通ればスルリと抜け出すことが可能です。
この性質のせいで、水族館ではタコが水槽から脱走する事件がしばしば報告されます。配管を通って隣の水槽へ行ったり、フタのわずかな隙間から出てきたりと、タコはその柔軟性と知能を活かして“脱獄”してしまうのです。
タコは擬態とカモフラージュの名人
タコのもうひとつの驚異的な能力がカモフラージュです。皮膚にある「クロマトフォア」という色素胞が伸縮することで体色を瞬時に変えられます。さらに「イリドフォア」や「ルコフォア」という細胞で光の反射を操り、色だけでなく光沢や明るさまでもコントロールできるのです。
これに加えて、皮膚の表面を盛り上げてデコボコにすることで、岩や海藻の質感まで再現してしまいます。中には「ミミックオクトパス」のように、ヒラメやウミヘビ、クラゲに似せて、まるで別の生物に変身するタコも存在します。これは捕食者を欺くための高度な生存戦略です。
タコには道具を使う知能がある?
実験では、タコが瓶のフタを器用に開けて中の餌を取り出したり、迷路を学習して最短ルートを覚えたりすることが確認されています。中にはココナッツの殻や大きな貝殻を持ち歩き、敵に襲われたときのシェルターに使うタコもいます。
こうした行動は「無脊椎動物なのに、まるで脊椎動物並みの知能を持つ」と評価され、研究者たちを驚かせています。タコのニューロン(神経細胞)はおよそ5億個。これは犬と同じくらいの数で、知能の高さを裏付けています。
タコの短命な一生には理由がある?
これほど高度な知能を備えながら、タコの寿命は驚くほど短いのも特徴です。多くの種類はわずか1〜2年、大型のミズダコでも3〜5年程度しか生きられません。
しかも繁殖を終えると、オスは交尾後に急速に衰弱して死に、メスも卵を守り続けて餌を取らず、やがて命を落とします。この「繁殖死」は、タコが進化の過程で選んだ戦略であり、「子孫を残すことが最大の使命」と考えれば納得できますが、やはり切なくもあります。
タコは謎に満ちた存在
2015年にタコのゲノム(全遺伝情報)が解読されました。その結果、脊椎動物に匹敵するほど複雑な遺伝子構造を持つことが判明し、特に神経に関わる遺伝子が異常に多いことが分かっています。こうした発見から、一部の科学者は「タコの進化は地球外生命体のようだ」と表現するほどです。
タコのまとめ
タコは、青い血と3つの心臓、9つの脳を持ち、自在なカモフラージュと高い知能で海を生き抜く生物です。知れば知るほど不思議で、科学的にもまだ解明されていない部分が多く、まさに“海の宇宙人”とも言える存在でしょう。